こんにちは!統失サラリーマンのころたんです!(^O^)
先日、対話のNUKADOKOさん主催のイベント「先進事例に学ぼう!対話(会)のはじめ方」第1回に参加しました。
その時間は、私にとってとても有意義で、深く納得することの多いひとときとなりました。
ゲスト・若杉逸平さんの姿に憧れて
ゲストとしてお話された若杉逸平さんは、長年高校教員として生徒と向き合い、現在は全国各地で対話の場をファシリテートされているそうです。
そのご経験からにじみ出る柔らかな存在感と、場に対するまなざしの深さに、私は強く惹かれました。
教員としてのご経験を土台に、今も多様な現場で「対話」の可能性を信じて動き続けている若杉さんの姿に、心から憧れを感じました。
「対話=共に生きること」という響き
会の中で、若杉さんが「対話とは共に生きること」とおっしゃったとき、私の中にすでにあった対話のイメージとぴたりと重なりました。
とても共感したのと同時に、印象的だったのは、若杉さんがその発言の前に「拡大解釈かもしれませんが」と一言添えていたことです。
一見、控えめな姿勢に見えるそのひとことに、私は深い誠実さを感じました。対話とは正しさを語る場ではなく、探究とゆるやかな共有の場だということを、あらためて思い出させてくれました。
自分にとっての「対話」とは
今回の場で、私自身も「対話とは何か」という問いをもう一度見つめなおす機会を得ました。
私は、対話とは誰かと共によりよく生きるための営みであり、最終的には完全に分かり合えないことを前提としつつも、それでも理解しようとする努力を手放さないことだと、あらためて納得しました。
そしてもうひとつ。
人はいつも、特定の立場だけで対話するわけではないということ。
たとえば親として、教師として、あるいは単なる一人の人として。
「立場を脱ぎ着しながら対話に臨む」という在り方が、違いを尊重し、共に生きるためにとても大切なことだと、深く実感しました。
「言葉」や「常識」を見つめなおす時間
会のなかで話題になった、「人権」「常識」「正解」「本音」「言葉」「概念」「本質」「理解」……これらの言葉に対して、私はたくさんの問いを持ち帰りました。
ふだん何気なく使っている言葉の奥にある、文脈や背景、時には暴力性すらも見つめなおすこと。
それは決して簡単ではないけれど、対話の場があったからこそ、その扉を開くことができました。
有料イベントに参加して思ったこと
今回は、対話のNUKADOKOさんの有料イベントへの初参加でもありました。
正直に言えば、参加費を支払うということには、やはり「それに見合う価値があるのか」と意識が向くものです。
でも、実際に参加してみて感じたのは、その価値をはるかに超える時間だったということ。
NUKADOKOさんは、ホストとして場を丁寧に整えながらも、対話の中ではひとりの参加者として自然に溶け込んでくれました。
その距離感が私はとても心地よく、嬉しかったです。
「対話のNUKADOKO」さんの活動紹介
最後に、今回の主催者である対話のNUKADOKOについても、少し紹介しておきたいと思います。
世界中で、毎日、24時間、どこかで「対話会」が開かれていたらよいな、と本気で思っています。
そう語る西森さんは、「生成的」「創発的」な対話の場をつくることをライフワークとし、その担い手を増やしていくことを願って活動されています。
2025年4〜8月にかけて開催されている「先進事例に学ぼう!対話(会)のはじめ方」は、すでに対話の場づくりを実践しているゲストを招き、その知恵と工夫を分かち合うシリーズ企画です。
以下に、対話のNUKADOKOさんのpeatixのHPを張りますので気になった方は見てみてください!(^^)!
https://peatix.com/group/16319012
今回の出会いと学びに、心から感謝しています。
「対話」という営みの奥深さと豊かさを、これからもゆっくりと噛みしめていきたいと思います。
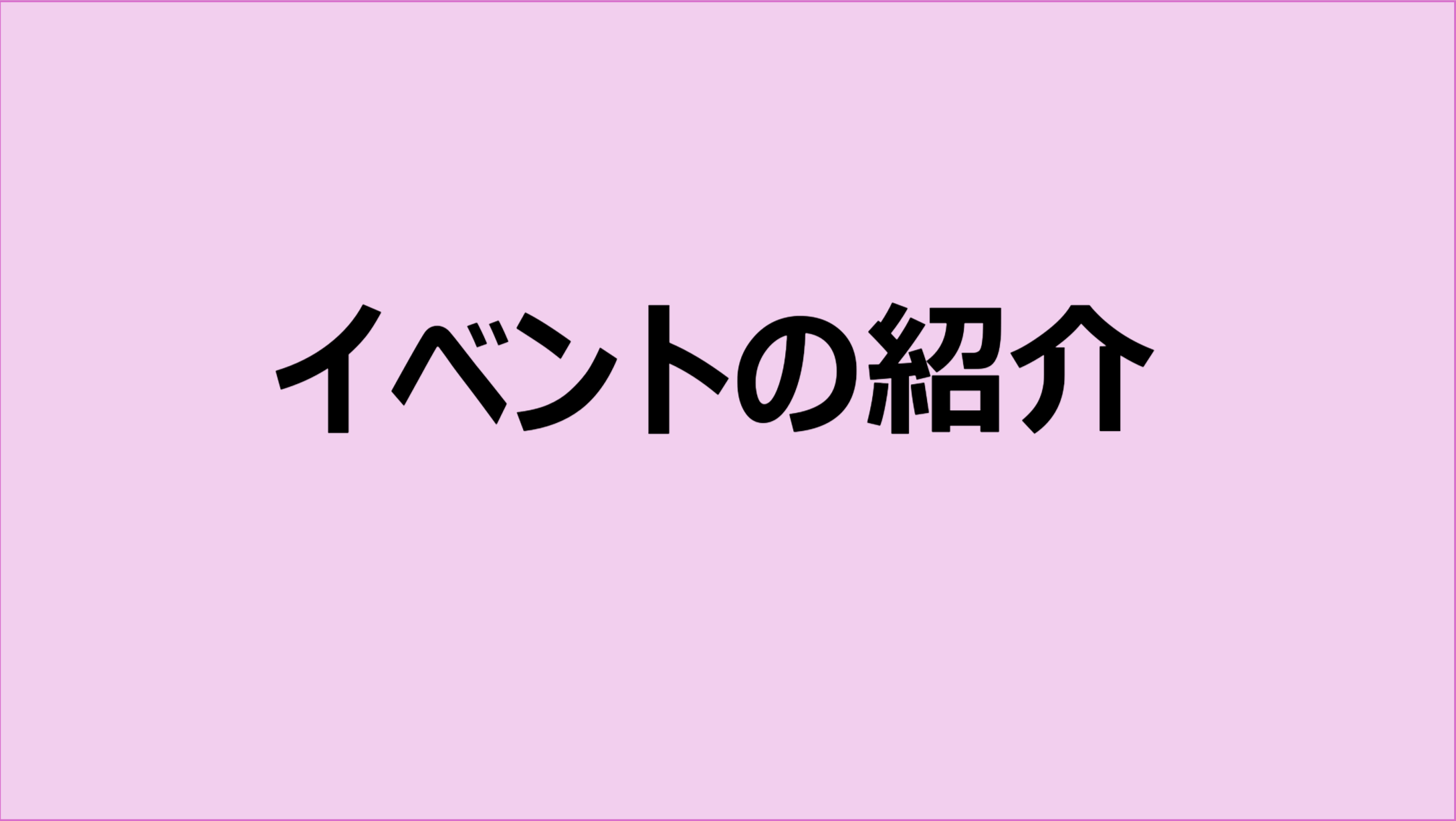


コメント